玄関ドアの老朽化を放置すると危険?リフォームの必要性をチェック
玄関ドアは、住まいの顔ともいえる重要な部分です。
しかし、長年使用していると劣化が進み、防犯性や断熱性が低下してしまうことがあります。
老朽化を放置すると、安全面や快適性に影響を及ぼすため、適切なタイミングでリフォームを検討することが大切です。
本記事では、玄関ドアの老朽化によるリスクと、リフォームの必要性について詳しく解説します。
この記事は、次の人におすすめです!
・家を建ててから玄関ドアの交換をしていない
・防犯面で玄関ドアの交換を考えている
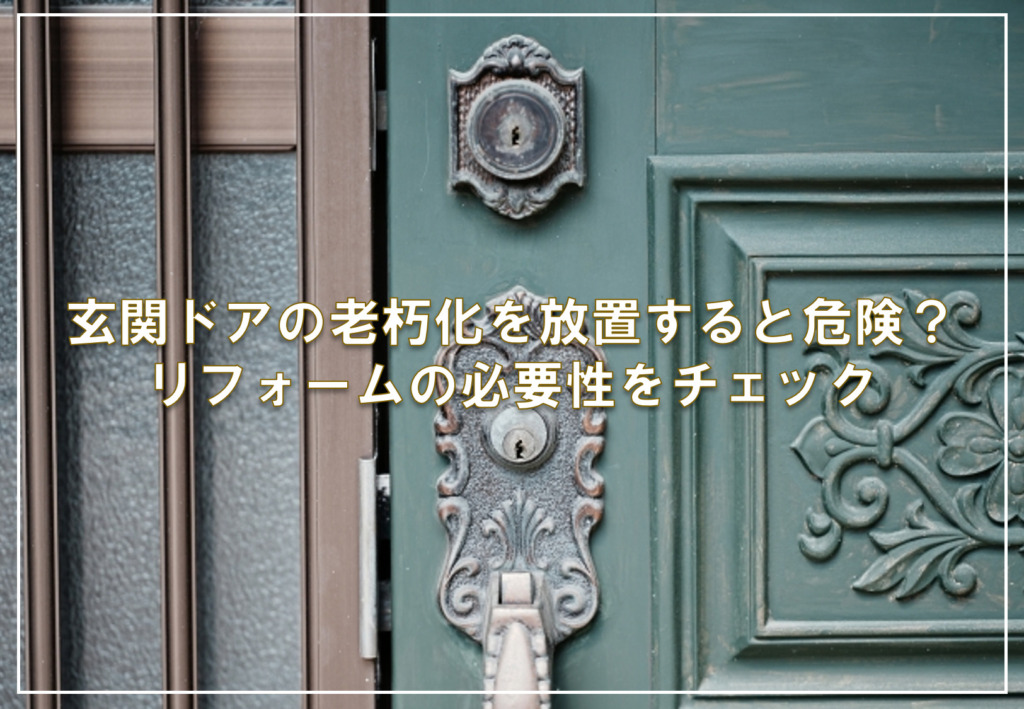
目次
1 玄関ドアの老朽化が引き起こす問題

玄関ドアは、毎日開閉を繰り返すため、少しずつ劣化が進みます。
劣化が進むと、さまざまな問題が発生し、住まいの安全や快適性に悪影響を与えます。
防犯性の低下
古くなった玄関ドアは、鍵やドア枠が劣化し、簡単にこじ開けられるリスクが高まります。特に、築年数の経過した住宅では、防犯性の低い鍵が使われていることもあり、空き巣の標的になりやすくなります。
断熱・気密性の低下
ドアの隙間が広がったり、素材が劣化したりすると、室内の暖かい空気が外へ逃げやすくなります。これにより、夏は冷房が効きにくく、冬は暖房の効果が低下するため、光熱費の増加にもつながります。
開閉の不具合
ドアの蝶番(ちょうつがい)やドアクローザーが摩耗すると、スムーズに開閉できなくなります。最悪の場合、ドアが閉まらなくなったり、逆に固くて開かなくなったりすることもあります。
- 玄関ドアの劣化が進むと、防犯性が低下し空き巣のリスクが高まる
- 断熱・気密性が落ち、室内の温度管理が難しくなり光熱費が増加する
- 開閉の不具合が発生し、日常の使い勝手が悪くなる
2 玄関ドアリフォームが必要なサイン

玄関ドアのリフォームが必要かどうかを判断するには、以下のようなサインをチェックしましょう。
鍵のかかりが悪い
鍵がスムーズに回らない、引っかかるような感覚がある場合は、錠前の劣化やドアの歪みが考えられます。防犯性を維持するためにも、早めの対策が必要です。
ドアの隙間が広がっている
玄関ドアと枠の間に隙間ができていると、気密性が低下し、外気が入りやすくなります。すきま風や虫の侵入が気になる場合は、ドアの歪みや劣化が進んでいる可能性があります。
ドアの表面が傷んでいる
木製ドアの場合は、表面が割れたり反ったりすることがあります。また、金属製ドアでは、錆びや塗装の剥がれが目立つこともあります。見た目の問題だけでなく、耐久性の低下にもつながるため、リフォームを検討しましょう。
開閉時に異音がする
ドアを開け閉めする際にギシギシと音がする場合は、蝶番の劣化やドアクローザーの故障が考えられます。放置すると、突然開かなくなることもあるため、早めの対処が重要です。
- 鍵のかかりが悪い場合は、防犯性の低下が懸念される
- 隙間が広がっていると、気密性が低下し冷暖房の効率が悪くなる
- ドアの傷みや開閉時の異音は、リフォームのサイン
3 玄関ドアリフォームのメリット

玄関ドアをリフォームすることで、見た目が美しくなるだけでなく、防犯性や断熱性が向上し、快適な住環境を実現できます。
防犯性の向上
最新の玄関ドアには、高性能な鍵(ディンプルキーや電子錠)や、こじ開けに強い構造が採用されています。防犯性を強化することで、空き巣のリスクを大幅に低減できます。
断熱・気密性の向上
断熱材が入ったドアや、気密性の高いドアを選ぶことで、室内の温度を快適に保ち、冷暖房の効率をアップできます。これにより、年間の光熱費を節約できる効果も期待できます。
デザイン性の向上
玄関ドアを新しくすることで、家全体の印象が大きく変わります。豊富なデザインやカラーバリエーションから選べるため、家の雰囲気に合ったドアを選ぶことが可能です。
開閉がスムーズに
最新のドアは、軽い力でスムーズに開閉できるよう設計されています。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、安全で使いやすいドアを選ぶことが大切です。
- 最新の玄関ドアは、防犯性が向上し空き巣対策に有効
- 断熱・気密性の高いドアを選ぶと、室内の快適性が向上し光熱費を節約できる
- デザイン性がアップし、家全体の印象が良くなる
4 まとめ
玄関ドアの老朽化を放置すると、防犯性や断熱性の低下、開閉の不具合などさまざまな問題が発生します。
リフォームのサインを見逃さず、適切なタイミングで新しいドアに交換することで、安全で快適な住まいを維持できます。
- 玄関ドアの劣化は、防犯性や快適性の低下につながる
- 鍵の不具合や隙間の広がり、開閉時の異音はリフォームのサイン
- 最新の玄関ドアに交換することで、防犯・断熱・デザイン性が向上
玄関ドアの状態を定期的にチェックし、必要に応じてリフォームを検討しましょう。
ハウジング重兵衛 編集部のプロフィール

リフォームを中心とした住宅業界
免許登録
・一級建築士事務所 登録番号 第1-2004-7311号
・国土交通大臣 許可(般-5)第25003号
・宅地建物取引番号(5)第13807号
資格情報
・一級建築士
・二級建築士
・インテリアコーディネーター


